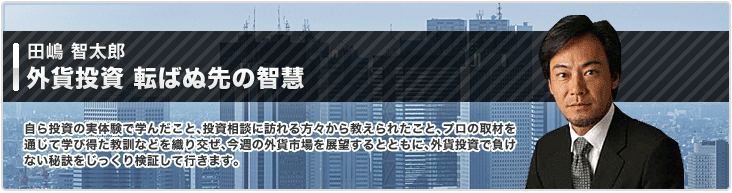先週末1日、米10年債利回りは一時4.20%台まで低下することとなった。この日は、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が米大学のイベントで講演しており、その内容に対して市場は「警戒していたほどタカ派的ではなかった」と受け止めた模様である。果たして、市場は何をそれほど「警戒」していたのだろうか。
ことの発端は先週28日に伝わったFRBのウォーラー理事の発言に対して、市場がやや過剰に強いドル売りで反応したことにあった。同理事は、単に「現在の政策が景気を減速させ、インフレを2%に戻すのに十分な位置にあると確信している」と述べたに過ぎない。ところが、市場は「来年の利下げに前向きであった」と勝手に拡大解釈した。
実際のところ、ウォーラー氏は「利下げが可能と判断されるようになるまでの政策判断のプロセス」などについて説明をしただけで、数カ月内の利下げの可能性になど一切触れてはいない。つまり、市場の解釈が過度に先走ったということになる。
結果、FRB関係者らは慌てて“火消し”に走り回る必要に迫られることとなった。30日に、米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は「FRBが利上げを完了したかどうかを考えるのは時期尚早」と述べ、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁もタカ派寄りの姿勢をアピールしていた。彼らの言動からは「FRBのメッセージが市場に誤った形で伝わってしまっているのであれば、それは正しく修正すべき」という強い意志が感じられた。
そのおかげもあり、30日にはドルが一旦強く買い戻される。むろん、そこには月末に絡んだ買い戻しの動きも関わっていたが、翌1日にパウエル議長が米連邦公開市場委員会(FOMC、12‐13日)のブラックアウト期間に入る前の最後の講演を行う予定であったことから、その内容に対する「警戒」も当然あったと思われる。
そして、ついに注目の講演が始まった。パウエル議長の口からはややタカ派的な発言も少なからず飛び出していたが、同時に足元の政策金利について「かなり引き締め的な領域に入っている」と述べたり、「来年に米国の消費や生産が減速する」との見方を示したりもしていた。むろん、これでは市場の早期利下げ期待に対する“火消し”には不十分ということで市場は米株買い、ドル売りで反応することとなった。
その結果、週末のドル/円は146円台まで下落することとなり、週のスタート時点(27日)より2.5円程度もドル安・円高方向に振れる動きとなった。
少し振り返ると、感謝祭前のポジション調整を主因とする大幅な下げ(21日)から切り返した後のドル/円は、前回更新分の本欄で触れたとおり、一目均衡表の日足の「基準線」と「転換線」に上値を押さえられる状態を続けていた。そして、先週のはじめからそれ以降は明らかに「転換線」を上値抵抗として意識する展開が続いている。
日足の「遅行線」が26日前の「雲」上限に達しており、このあたりで一旦下げ渋る可能性もあるが、なおも基本は戻り売りスタンスで臨みたいところであり、当面の下値の目安としては7月安値から直近高値までの上げに対する38.2%押しの水準=146.30円何処から50%押しの水準=144.60円処あたりを考えておくこととする。
なお、前回はクロス円についても「戻り売りのタイミングをうかがう局面」と述べ、実際に先週のユーロ/円、ポンド/円はショートが正解であった。
ただ、目下はユーロに比べるとポンドの方が強い。先週30日に発表された11月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)が予想を下回ったこともあり、市場では「欧州中央銀行(ECB)の4月利下げ開始」を織り込む動きが強まっている。よって当面、ポンドの下値はある程度限られるものと見ておきたい。
(12/04 07:00)
FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-