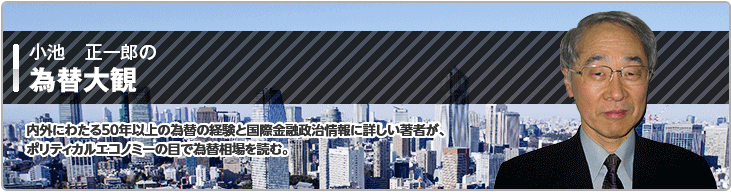今年はニクソンショックから53年。うち52年間、筆者は為替市場に関わってきた。先週からの一週間(7/31-8/7)の円の急騰劇は、為替相場変動史に新たな1ページとなったと捉えている。今回は為替だけでなく、金利、株式、商品すべての市場が大変動となったことで、いわゆるインターマーケットの一体化が鮮明になったことだ。ただこの劇の幕は下りていない。
市場取引で完全にコンピューターが担ってきてから年月が経っているが、取引の為の情報処理や実行スピードは幾何学的に高速化の度合いが高まっている。その中で人間が生き残る道は何か、機械処理だけに任せてよいか、大げさなことではなく、筆者の頭の中に渦巻いている。このような変動劇を考える中で、出てきた言葉は、取引手法として、アヘッド・オブ・カーブの技を磨くことと、運用手法として分散投資の範囲種類の拡大である。
アヘッド・オブ・カーブとは、見えないカーブの先を読むことで、筆者はその一環として当コラムで継続的に相場見通しを行っている。52年の歴史の中で、予想期間の違いこそあれ、定期的に実践してきたが、当たることもあれば予想通りにいかないこともある。予想の難しさからの克服はまだできていない。例えば先週のコラムでのドル円予想(7/31からの一週間)は149.50-153.50円だった。ところが実績は141.67円(8/5)-153.89円(7/31)、なんと12.22円の変動幅(変動率は、高値から1週間で7.9%)となり、大外れであった。
まさに特別と言えば特別であったが、個人的には、忸怩たる思いである。その理由は、①市場の変化(IT全盛、高速化)は認識していたが、先読みが不足していたこと、②ポリティカルエコノミーを専門としていたにもかかわらず、海外筋が結論を急いだことを読めなかったことである。①については、投機家の特性やポジション額や利食いのタイミングを過小評価したことだ。特に市場が薄い時(早朝や日本だけが休日など)に、波状攻撃が繰り返されることで、弾(取引額)が少ロットであっても、いわゆるコスパがよくなるので、投機家は多用する傾向があることをもっと織り込むべきであった。
また②においては、経験則からくるものだが、大相場になったのは、すべて政治が火付け役であったことを重く受け取るべきであったということだ。大変動の歴史の始まりは、国際通貨制度を根本的に変え、変動相場制の始まりとなった1971年のニクソンショックだが、個人的には、まさに米国でディーリングに明け暮れていたさなかに起こった、1日で約20円(180-200円)乱高下した1978年の米国カーター大統領のドル防衛策発表、そして1985年プラザ合意(200円突破)、1987年ブラックマンデー、1994年には米国の日本企業叩きで100円を突破、1997年のアジア通貨危機、1999年のユーロ導入と続く。
そして21世紀に入り、2008年リーマンショック、2010年のギリシャショック、2016年英国のEU離脱、米トランプ大統領就任、2020年からのコロナショックを経て、2022年ロシア・ウクライナ戦争勃発が発生。今年は日米金利差の拡大で37年半ぶりの円安となったが、これは米国がドル高を引き下げることを決めたG5会議以降のドル安の時期に並んだことになる。すべて政治が為替相場を決めたと言える。
今回の円急騰劇は、日銀総裁の記者会見での追加利上げ示唆発言が尾を引いたことで始まったことだが、今日は内田副総裁の追加利上げ慎重発言が火消しになった。まさに政治家(中央銀行も含めて)の発言が相場を作る恰好な例となった。結果ドル円は147円台に上昇。今回の円急騰劇ではまだ、反転模様が始まったばかり。これで一気にドル円が上昇するとは考えにくい。
さて、今後1週間の相場見通しであるが、ドル円は来週14日の米CPIを始め米国の景気動向を背景に、144.50-148.50円と荒い展開を予想する。一方欧州通貨は、ユーロドルは1.0800-1.1100と小幅ユーロ高、対円では159.00-162.00円とユーロ安継続と予想する。そして英ポンドドルは1.2700-1.2900と小幅ポンド安と予想する。
(2024/8/7、 小池正一郎)